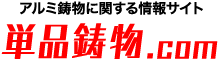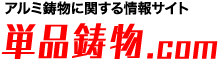こんにちは、営業部長の藤本です。
皆様、お盆休みは満喫できましたか?
今年は9連休のところも多かったみたいですね。
本日より気持ち切り替えて頑張っていきましょう。
今回は鋳物屋が頭を悩ませる代表的な欠陥の一つ「鋳巣」について書きたいと思います。
「ちゅうす」または「いす」と読みます。
鋳巣とは?
鋳造巣とは、鋳物内部にできる空洞や気泡のことを指します。代表的な種類には以下があります。
- ガス巣(ピンホール):ガスが抜けきれずに固まったもの
- ヒケ巣:凝固時の体積収縮で空洞が残ったもの
- 巻き込み巣:湯流れの乱れで空気や酸化皮膜が巻き込まれたもの
外からは見えないことも多く、機械加工後やX線検査で発見されるケースが一般的です。
鋳巣ができる原因
1.ガスによるもの
アルミ溶湯は水素を吸いやすい性質があります。
溶解時に吸収した水素が、凝固時に放出されきれずに気泡となって残ると「ガス巣」になります。
2.凝固収縮によるもの
アルミ合金は凝固時に約6%の体積収縮を起こします。
これを補えないと、鋳物内部に空洞(縮み巣)が残ります。特に肉厚部や冷えの遅い部分に発生しやすいです。
3.湯流れによるもの
鋳造時に湯口から流れ込む溶湯が乱流になると、空気や酸化皮膜を巻き込みます。
これが「巻き込み巣」となって内部に残ります。
鋳巣の対策方法
1.ガス対策
- 溶解時の脱ガス処理(弊社ではGBFという装置を使用し微細なアルゴンガスを吹き込み、ガスや介在物をアルゴンガスの気泡に吸着させて浮上させます)
- 溶湯の清浄化(フラックス処理、フィルター使用)
2.凝固対策
- 押湯の適切な配置で凝固収縮を補う
- 肉厚差を減らした設計を行う
- 法案や冷やし金により冷却速度を制御して凝固方向をコントロール
3.湯流れ対策
- 湯口設計の最適化(直線的で穏やかな流れにする)
- フィルターの設置で酸化物の巻き込みを低減
- 溶湯注入速度の管理で乱流を防ぐ
鋳巣は種類により対策のポイントが違うのがやっかいなところです。
まずは、発生位置や形状をよく観察して、原因を見極める事から始まります。
ここは長年の経験がないと分からないところです。
鋳物に鋳巣はつきものですが、当社では様々な対策を行い、鋳巣のない鋳物を安定して造れるよう日々努力しております。
アルミ鋳物の試作・少量ロット量産はお任せ下さい。
4種の製法を活かし、その製品に最適なプロセスでご提案いたします。
鋳物のお困りごとがありましたら弊社問合せフォーム迄お待ちしております!